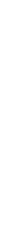column コラム
2025.02.28
相続した不動産の固定資産税はいつから支払う?支払い義務者や手続きを解説
皆さん、こんにちは。SAKURA財産形成承継の大原です。
「相続した不動産の固定資産税の支払い義務者は誰?」「親から相続した実家の固定資産税はいつから支払う必要があるの?」など、弊社では不動産の相続に関する固定資産税についてのご相談を多くいただきます。
実はこの固定資産税の問題は、相続直後だけでなく、将来にわたって家族の資産形成に大きな影響を与える可能性があります。
今回は相続した不動産の固定資産税について、誰に、いつから支払い義務が発生するのかや、よくあるトラブルへの具体的な対策などについて、わかりやすくご説明します。
相続不動産の固定資産税|基礎知識
固定資産税は、毎年1月1日時点での所有者に課税される税金です。
相続の場合、被相続人が1月1日から相続開始日までの分と、相続人が相続開始日の翌日から12月31日までの分をそれぞれ負担することになります。
たとえば、6月15日に父が亡くなり実家を長男が相続した場合、1月1日から6月15日までの固定資産税は父の相続財産から支払い、6月16日から12月31日までの分は長男が支払うことになります。
また、相続登記が完了していなくても、実質的な所有者である相続人に固定資産税の支払い義務が発生します。
この点は多くの方が誤解されやすいポイントです。
たとえば、「まだ相続登記が済んでいないから、固定資産税の支払いは待ってもよいのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。
相続は被相続人が亡くなった時点で発生し、その時点で相続人が不動産の所有権を取得するため、登記の有無に関係なく、固定資産税の支払い義務も発生します。
この誤解により支払いが遅れると、延滞金が発生したり、最悪の場合、差し押さえなどの滞納処分を受けるリスクもあります。
特に、相続人が複数いる場合は、登記が完了していなくても、法定相続分に応じて連帯して納税義務を負うことになります。
なお、所有者が亡くなった場合は、固定資産税の納税通知書の送付先変更手続きを市区町村の担当窓口に届け出る必要があります。
この手続きは相続登記とは別の手続きですので、早めに行っておきましょう。
相続時によくある問題とその対応
1. 複数相続人での負担方法
Aさんの事例では、父から相続した賃貸マンションの固定資産税を兄弟3人で負担することになりました。
しかし、支払い方法や負担割合について話し合いがつかず、未納が発生してしまいました。
このようなケースでは、原則として法定相続分に応じた負担となりますが、話し合いにより別の割合で分担することも可能です。
ただし、その場合は書面(遺産分割協議書と言います)での取り決めが重要です。
具体的な対応策としては、以下のような方法が考えられます。
- 相続人の一人が固定資産税を立て替えて支払い、他の相続人から後日精算する
- 共有名義の銀行口座を開設し、各自が負担分を振り込んで支払いに充てる
- 賃貸収入がある場合は、その収入から固定資産税を支払う専用の口座を設定する
特に重要なのは、支払いの方法や時期、精算方法について、明確に取り決めておくこと。
この際には、以下の内容を含めるようにしましょう。
- 各相続人の負担割合
- 支払いの期限と方法
- 立替払いが発生した場合の精算方法
- 遅延が発生した場合の取り扱い
2. 相続人が見つからない場合の処理
Bさんの場合、相続人の一人と長年連絡が取れない状態でした。
このような場合、連絡が取れる相続人だけで固定資産税を負担し、後日精算する方法があります。
具体的には、次のような方法をとります。
- 不在者財産管理人の選任申立てを行う
- 所在不明の相続人の法定相続分を供託する
- 相続人の調査を専門家に依頼する
3. 予期せぬ税額変更への対応
固定資産税は3年ごとに評価替えが行われます。
Cさんの事例では、相続後の評価替えで税額が大幅に上昇し、予定していた賃貸収入では支払いが厳しくなってしまいました。
このような状況に備えるための一般的な対策は以下の通りです。
- 評価替えの時期を確認し、早めに概算額を市区町村に問い合わせる
- 固定資産税の支払い予備費として、賃料収入の一部を積み立てておく
- 納税通知書が届いたら、すぐに内容を確認し、疑問点があれば市区町村の担当窓口に相談する
また、税額が高いと感じた場合の対応としては、以下のような選択肢があります。
- 固定資産評価証明書を取得し、評価額が妥当かどうかを確認
- 必要に応じて固定資産評価審査委員会に審査の申出を行う
- 減額措置が受けられるかどうかを担当窓口に相談
万が一、これらの対応をとっても納税が難しい場合は、相続税が払えない?困った時の6つの対処法で紹介しているような方法をとることも選択肢の一つです。
なお、これらの対応を行う場合は、期限や手続きの要件が厳格に定められていることが多いため、専門家のアドバイスのもとで進めていく必要があります。
まとめ
このように、相続不動産の固定資産税対策は、単なる税金の支払い方法だけでなく、不動産の活用方法や家族間の話し合いなど、様々なことを検討・決定していかなければなりません。
特に注意したいのは、対策の多くは実施までに時間がかかるということです。
相続が発生してから慌てて対策を考えるのではなく、早い段階から専門家に相談し、計画的に準備を進める必要があります。
SAKURA財産形成承継株式会社では、不動産の相続対策から活用方法まで、専門家による総合的なアドバイスを提供しています。
例えば、相続した実家を収益物件化して固定資産税の負担を軽減できた事例や、家族信託を活用して円滑な資産承継を実現した事例など、様々な成功事例があります。
相続した不動産の固定資産税でお悩みの方は、ぜひ一度当社のお問い合わせフォームにご相談ください。
経験豊富な専門家が、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

 CONTACT
CONTACT CONTACT
CONTACT