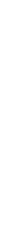column コラム
2025.02.15
「二次相続」対策、していますか?―――子ども世代に相続する前に知っておきたい話
皆さん、こんにちは。SAKURA財産形成承継の大原です。
相続対策について考えるとき、多くの方が一次相続(両親のいずれか一方が亡くなった際に発生する相続)にばかり目を向けがちです。
しかし、実は「二次相続」への備えも同じくらい大切です。
二次相続とは、相続した財産が再び相続されることを指し、特に配偶者が相続した財産を子どもが相続するケースが多く見られます。
実はこの二次相続への対策が不十分で、子ども世代に思わぬトラブルを招いてしまうことは少なくありません。
今回は、そのような事態を防ぐために、今から考えておくべき二次相続の課題と対策についてご紹介します。
よくある二次相続トラブル
二次相続のトラブルは千差万別ですが、例えば次のようなケースがあります。
ケース1:予想外の相続税負担に直面
Aさんの事例では、母が配偶者控除を使って父の不動産を相続しました。
当時は「配偶者控除があるから大丈夫」と考えていましたが、その後10年で地価が上昇。
母の相続時には予想以上の評価額となり、兄弟で多額の相続税を負担することになりました。
結果として、教育費の捻出や住宅ローンの返済計画など、家族の生活設計を大きく見直さざるを得ない状況に追い込まれてしまいました。
ケース2:認知症発症後の相続で家族間対立
Bさんの場合、母の認知症発症後に相続が発生。不動産の活用方法を巡って兄弟間で意見が分かれ、話し合いは平行線をたどりました。
「売却して現金化したい」「賃貸経営を続けたい」「実家に住み続けたい」など、それぞれの主張が対立。
結果的に解決までに多大な時間と労力、さらには弁護士費用などの余計な支出が必要となってしまいました。
トラブル防止のための「二次相続」対策
二次相続対策には、様々な選択肢があり、組み合わせることでより大きな結果が期待できるものもあります。
以下では5つの主な対策を紹介しますが、最適な対策や実行に移すタイミングを見極めるには、相続の専門家に相談する必要があります。
1. 生前贈与の活用
生前贈与には、毎年110万円まで贈与税がかからない「暦年贈与」と、2,500万円まで贈与時の贈与税を相続時まで猶予できる「相続時精算課税制度」があります。
例えば、マンションの一室を子どもに贈与し、住宅ローンの返済を子ども世代のうちから始めてもらう方法があります。
これにより、将来の相続財産を減らしながら、子どもの資産形成も支援できます。
また、教育資金の贈与なら1,500万円まで、結婚・子育て資金の贈与なら1,000万円まで非課税で贈与できる制度もあります。
お孫さんの教育費を見据えた対策としても活用できます。
2. 不動産の評価額対策
・収益不動産化
実家や賃貸マンションをリノベーションして収益不動産化することで、相続税評価額を下げられる可能性があります。
例えば、実家の一部を賃貸スペースにリフォームして収益物件とすることで、相続税評価額が下がるケースがあります。
・区分所有化
一つの大きな不動産を区分所有化することで、将来の相続時に分割しやすくなります。
例えば、賃貸マンションを区分所有化して、相続人ごとに違う階を相続するといった対策が可能です。
3. 家族信託の活用
認知症になった場合の不動産管理が心配な方におすすめの対策です。
例えば、母親が認知症になった場合でも、信頼できる家族(例:長男)を受託者として不動産の管理・処分を任せることができます。
4. 不動産の法人化
相続税対策として不動産を法人化する方法もあります。
例えば、賃貸マンションを所有している場合、これを法人化することで、以下のようなメリットが得られます。
- 相続税の評価額を下げられる可能性がある
- 法人の株式を少しずつ贈与することで、段階的な承継が可能
- 不動産所得を給与所得等に振り替えることで、相続財産を減らせる
ただし、法人化には設立費用や維持費用がかかるため、規模や収益性を考慮して慎重に検討する必要があります。
5. 生命保険の活用
相続税の支払いに備えて、生命保険に加入することも有効な対策です。
生命保険金には「死亡保険金の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)」があり、相続税の支払い資金として活用できます。
なぜ「二次相続対策は、早めが肝心」なのか?
「二次相続対策は、早めが肝心」と言われます。主な理由は以下の3点にあります。
「まだ自分は元気だから」と後回しにせず、早い段階で専門家に相談する必要があります。
1.認知症リスクが高まる
現在、65歳以上の約4人に1人が認知症またはその予備群と言われています。
認知症になると新たな対策を講じることが難しくなるため、早めの備えが重要です。
2. 対策の効果が出るまでに時間がかかる
例えば、不動産の収益物件化や法人化は、対策の効果が表れるまでに数年かかることもあるため、相続発生時に慌てて対策を取っても、十分な効果が得られない可能性があります。
3. 家族での合意形成に時間がかかる
相続対策には家族全員の理解と協力が必要です。特に複数の相続人がいる場合、話し合いと合意形成には相当な時間が必要となります。
まとめ
二次相続の問題は非常に複雑で、最適な対策は相続ごとに異なります。
定期的に税制が改正されることも踏まえると、あらかじめ最新の情報を把握しておく必要もあります。
手続きをスムーズに進めたい、後悔のない選択をしたいと考えるのなら、専門家に相談することが賢明です。
SAKURA財産形成承継株式会社では、不動産売買・管理から資産形成、相続対策まで、各分野の専門家による幅広いサービスを提供しています。
例えば、不動産の収益物件化と生前贈与を組み合わせることで相続税を大幅に圧縮できた事例や、家族信託を活用して認知症に備えながら円滑な資産承継を実現した事例など、様々な成功事例があります。
一人ひとりのお客様に合わせた、最適な解決策をご提案いたしますので、お悩みの方はぜひ一度当社のお問い合わせフォームまでご相談ください。

 CONTACT
CONTACT CONTACT
CONTACT