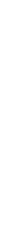column コラム
2025.10.30
相続人が多すぎる!“共有名義地獄”の回避マニュアル
皆さん、こんにちは。SAKURA財産形成承継の大原です。
「みんなで平等に分け合えば不満が出ないだろう」
「細かい取り決めを今決めるのは大変だから、共有にしておけば安心」
そんな発想から、相続した不動産を兄弟姉妹で共有するご家庭は少なくありません。
しかし実際には、修繕や売却といった意思決定に全員の合意が必要となり、話し合いが長期化するケースが多発しています。
結果として資産価値が下がり、固定資産税や管理費の負担だけが積み重なる———これが俗に言う「共有名義地獄」です。
今回のコラムでは、このような事態に陥る原因と回避のための具体策を、実例を交えてわかりやすく解説します。
すぐわかる“共有名義地獄”リスク診断
相続で家を兄弟姉妹と共有している、もしくは共有することにしている方は、こんなことに心当たりはありませんか?
◻︎相続人が多く、「誰が決めるのか」を話し合っていない
◻︎固定資産税や修繕費をなりゆきで誰かが立て替えている
◻︎鍵の管理や修理の連絡を「誰が担当するのか」が曖昧
◻︎将来その家を「売るのか、残すのか」方向性を決めていない
◻︎相続登記(不動産の名義変更)の期限があることを知らない
こうした状態が重なると、いざという時に話し合いが止まり、家計にも家族関係にも大きな負担を残します。
5つのうち2つ以上当てはまれば要注意。
これを機に、どうすればリスクを抑えられるのか考えておく必要があります。
「とりあえず」で共有名義にしてしまうと…
もちろん共有名義にすること自体が問題なのではありません。
事前にルールを決めずに「とりあえず」で共有してしまうことが、後々のトラブルにつながるのです。
失敗事例:話し合いが進まないAさん一家
Aさんのご家庭では、お父様が遺した自宅を兄弟姉妹4人で共有することにしました。
当初は深く考えずに「みんなで持てば公平」と思っていましたが、売却か保有かで意見が分かれ、結論が出ないまま月日が経過。
固定資産税や修繕費は稼ぎの良い長男が「いったん僕が立て替えておくよ」とお金を出していましたが、気づくと総額は数百万円に膨らんでいました。
「これ以上持っていても仕方ない」とようやく売却することにしたものの、老朽化が進んでいたため、売却価格は当初より大幅に下落していました。
議論に議論を重ねた結果、3年かけて「自宅を売却し、代金を4人で分ける」ことでようやく合意に至りました。
ただしその際、長男が立て替えていた固定資産税や修繕費を清算する必要があり、取り分は当初の想定より大幅に減少。
資産価値も家族関係も損なわれ、「もっと早く方向性を決めていれば…」と悔やむ結果となりました。
共有名義地獄を回避するには?3つの“王道の解決策”
共有名義のトラブルを避けるには、大きく分けて3つの方法があります。それぞれの特徴を押さえておくことで、自分たちに合った選択肢を考えやすくなります。
① 遺産分割で単独名義にする(代償分割)
| 向いているケース | 家を引き継ぎたい人が明確にいる場合/「住み続けたい」「思い入れがある」と考える相続人がいる場合 |
| 必要な準備 | 他の相続人に渡す代償金の資金計画(現金・金融資産・ローンなど) |
不動産を誰か一人が相続し、他の相続人には現金などで代償を支払う方法。
たとえば長男が家を引き継ぎ、他の兄弟姉妹には金融資産を分配する形です。全員が不動産を共有し続ける必要がないため、意思決定がスムーズになります。
ただし代償金の準備が必要であり、資金計画を立てておくことが欠かせません。
② 持分を買い取る・第三者へ売却して集約する
| 向いているケース | 家を使わない人が多い/「早く現金化したい」ニーズが強い場合 |
| 必要な準備 | 売却に向けた不動産の評価額確認、買い取り資金や税金・仲介手数料の試算 ※専門家のサポート必須 |
誰かが他の相続人の持分を買い取ったり、不動産全体を売却して現金で分け合う方法。
「もう家を使わない」「資産を現金化したい」というニーズが強い場合に向いています。
売却代金は明確に分けやすい反面、市場価格の変動や買い手の有無に左右されやすい点に注意が必要です。
③ 家族信託で意思決定を一元化する
| 向いているケース | 相続人が多い/将来の認知症リスクに備えたい場合 |
| 必要な準備 | 信頼できる受託者の選定、信託契約の設計 ※専門家のサポート必須 |
近年注目されているのが「家族信託」です。
信頼できる家族を受託者に指定し、その人が不動産の管理や処分を一任される仕組みです。相続人が多くても意思決定が一本化され、スムーズに進めやすくなります。
また、将来的に親が認知症になった場合でも財産の凍結を防げるというメリットがあります。
ただし契約の設計が複雑になるため、専門家のサポートが必須です。
今日からできる5ステップ
共有名義のリスクを減らすために、特別な準備がなくても今日から始められることがあります。
まずは以下の5ステップから始めてみましょう。小さな一歩の積み重ねが、共有名義地獄を避ける最大の近道です。
ステップ1:専門家に相談してみる
最初に税理士や司法書士、不動産会社などのプロフェッショナルに相談することで、必要な情報や進め方が明確になります。
無料相談を活用すれば気軽に始められます。
ステップ2:相続人をリスト化する
兄弟姉妹やその配偶者、子どもなど、関係する人を紙に書き出し「誰が相続人か」を整理します。
ステップ3:費用の状況を確認する
固定資産税や修繕費がいくらかかっているか、直近の請求書や通帳で確認します。
ステップ4:負担のルールを話し合う
「誰が立て替えるのか」「いつ精算するのか」を決めておくだけで、後のトラブルを防げます。
ステップ5:将来の方向性を話題に出す
売却するのか、持ち続けるのか───結論を出せなくても「話すこと」自体が大切です。
まとめ
「共有名義にしておけば、とりあえずは安心」と思われがちですが、実際には意思決定が止まり、資産価値や家族関係を損なうハイリスクな選択肢になってしまう可能性があります。
大切なのは、問題が起きてから慌てるのではなく、事前にルールを決めて準備しておくこと。
今回ご紹介した5つのステップを実践すれば、リスクを大幅に減らすことができます。
私たちSAKURA財産形成承継株式会社では、相続対策・不動産管理・資産活用をワンストップでサポートしています。
「うちも共有名義になるかも」「どこから始めればいいかわからない」と感じた方は、まずはお気軽に当社のお問い合わせフォームからご相談ください。
経験豊富な専門家が、あなたのご家族に「とりあえず」ではない、最適な解決策をご提案いたします。

 CONTACT
CONTACT CONTACT
CONTACT