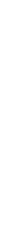column コラム
2025.04.21
収益物件相続の落とし穴と対策――相続税評価額から管理委託まで完全解説
皆さん、こんにちは。SAKURA財産形成承継の大原です。
「父から相続した築25年のアパート。入居者からの苦情が絶えず、思いがけない修繕費用が重なって、気づけば年間300万円もの赤字に……。
このままでは建物の価値がどんどん下がってしまうのではないかと、不安で夜も眠れません」
これは、当事務所に相談に来られた60代男性のお言葉です。
アパートなどの収益物件を相続した場合、相続直後の対応が遅れると、このように家賃収入が修繕費用で消えてしまったり、入居者とトラブルになったりすることが少なくありません。
今回は、2024年に大きく変わった法律を踏まえて、収益物件の相続でやるべきことを分かりやすく解説します。
相続発生後まずやるべきこと
2024年4月から新しい法律がスタートし、不動産を相続したら3年以内に必ず「相続登記」(所有者の名前を変更する手続き)をしなければならなくなりました。
この手続きを忘れると10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されます。
相続が発生したらまず以下のことを確認しましょう。
- 登記に必要な書類はそろっているか
- 相続人は誰で、どのくらいの割合で相続するのか
- いつまでに登記の手続きを済ませる必要があるか
また、建物の家賃収入については、遺産分割(誰がどの財産を相続するか決めること)が済むまでの間、原則として法定相続分(法律で定められた相続の割合)に応じて各相続人に受け取る権利があります。
例えば、配偶者と子供2人の場合、配偶者が2分の1、子供が各4分の1ずつとなります。
話し合いがまとまらない場合、具体的にやるべきことは、
- 管理会社に相続が発生したことを書面で連絡する
- 相続人それぞれの取り分に応じて家賃の振込先を決める
- 入居者に相続の発生を知らせる文書を送る(管理会社経由)
- 必要な書類をそろえる(固定資産税の評価証明書など)
- 相続人同士で話し合い(建物の管理方法、費用の負担など)
特に入居者とのトラブル防止のため、できるだけ早く管理会社などを通じて「当面は今までと変わらず運営します」といった内容の文書を送ることをおすすめします。
また、まだ受け取っていない家賃がある場合は、その家賃も相続財産に含まれますので、しっかり確認しましょう。
建物の価値をどう評価するか
2024年1月から、マンションやアパートの評価方法が大きく変わりました。
具体的には、建物の実際の価値と税金の計算で使う価値の差が大きい場合、新しい計算方法が使われることになりました。
また、建物の価値を正しく評価するためには、以下の点をチェックする必要があります。
- 過去3年間の家賃収入の変化
- 空室の状況(近くの似た建物と比べてどうか)
- 建物の管理状態と修繕の必要性
- 今までの修繕履歴と、これから必要な修繕
- その地域の将来性(再開発計画や新しい駅ができる予定はあるかなど)
2024年からの税制改正では、他にも以下のような重要な変更がありました。
- 生前贈与した財産を相続財産に加える期間が3年から7年に延長
- 相続時精算課税制度で、110万円の基礎控除(税金がかからない枠)が新設
正確に価値を計算し、その後適切な対応をするためには、専門家の力を借りる必要があります。くれぐれも後回しにせず、早い段階で相談する必要があります。
収支計画と管理の実務
アパート経営を取り巻く環境は大きく変化しています。
人口減少や相続税法改正による新築物件の増加など、経営環境は厳しさを増しています。相続したアパートを継続して経営するか、売却するか、以下の3つの視点から判断しましょう。
立地条件からの判断
好立地(駅近・都市部)の場合、表面利回り7%以上、実質利回り4%以上を目安に継続を検討できます。
しかし立地に不安がある場合、今後の収益低下リスクを考慮し、築年数が浅いうちの売却を検討すべきです。
管理負担からの判断
管理会社への委託が可能でも、以下の業務は避けられません。
- 管理会社を介した入居者対応(退去時対応)
- 収支管理(確定申告、修繕費用の積立)
- 大規模修繕の判断(例:築20年で約5,000万円規模になることも)
日常的な管理負担を避けたい場合は、売却を検討しましょう。
相続人の構成からの判断
複数の相続人がいる場合、アパート経営の継続には全員の合意が必要です。
家賃収入の分配方法や将来の修繕費用の負担などで意見が分かれやすく、共有での運営は避けなければなりません。この場合、売却して現金化し、公平な分配を検討しましょう。
なお、売却する場合でも、修繕履歴や収支状況を整理し、物件の価値を適切に評価できる状態にすることが重要です。
いずれの場合も、あらかじめ専門家にしておくことで、格段にスムーズに手続きを進めることができます。
まとめ
収益物件の相続では、専門的な知識と適切な対応が必要です。特に2024年は制度が大きく変わったため、登記の義務化や評価方法、税金の面で注意が必要です。
カギとなるのは「早めの専門家への相談」。あらかじめ困ったら頼れる専門家を見つけておくことで、その後の動きがスムーズになる可能性が高くなります。
SAKURA財産形成承継株式会社では、収益物件の相続に関するご相談に対して、多角的なサポート体制を整えています。
例えば、相続税理士による節税シミュレーションの作成、金融機関と連携した相続資金の調達、信頼できる工事会社の紹介による修繕費用の適正化など、お客様の状況に応じた総合的なソリューションをご提案いたします。
独自のネットワークを活用し、必要に応じて各分野の専門家と連携することで、相続から収益物件の管理運営まで、一貫してサポートいたします。
相続についてのご相談は、当社のお問い合わせフォームから。経験豊富な専門家が、最新の法律に基づいて最適な解決策をご提案いたします。

 CONTACT
CONTACT CONTACT
CONTACT